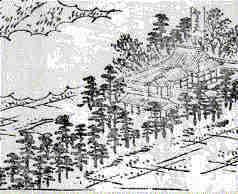府守神社 府守神社
和歌山市府中1089 ゼンリン<
交通案内
阪和線 天王寺→紀伊 西1km線路沿い
祭神
倭武命
由緒
貞観十七年(875年)、此の地におかれた紀伊國國府の鬼門の守護神として鎮座、中古白鳥の宮とも聖天宮とも称した。
明治以後旧名の府守神社に復したが、拝殿正面には聖天宮と記されている。
紀伊国府は六町四方とされているが、その場所は定かではないが、この神社は国府の北東に当たるはずである。神社鳥居脇に国府跡の碑がたっている。
お姿
本殿は瓦葺き流れ造。
この辺りは古代から人が住んでおり、弥生時代中期から古墳時代前期の住居跡が出ている。円形から方形への変化が読みとれる遺跡である。
拝殿と本殿

鳥居 左隅に国府跡の碑

お祭り
10月 5日 秋季例大祭
紀伊国名所図絵 聖天宮
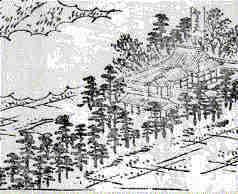
| 紀伊續風土記 巻之九 名草郡第四 直川荘 府中村から
○歓喜天社 境内五十間 百間 馬塲
本 社 方二間 拝殿 廳
村中平林といふ所の東にあり 按するに本國神名帳に従四位上府守の神あり
三代實録に貞観十七年奉授紀伊ノ國従五位下府中ノ神従五位上ヲとあり府守ノ神府中ノ神は一にして國府を守り給ふ神と聞ゆれは當社若くは此神にやあらん
三代實録石見ノ國に府中ノ神あり
天慶七年(944年)筑後諸神記に郡守神といふあり 社地古く広大にして處の氏神と崇むるは此故ならん
中古浮屠氏盛にして聖天なとといふ名を設けて佛に引入たるなるへし 又歓喜天の祭禮といふ事を聞さるに此神には祭禮ありて六月廿八日九月五日古より定り来りなる由なれは決して府守ノ神にして聖天にはあらさるへし
當社の西に天王森といふあり |
紀の国古代史街道
神奈備にようこそに戻る
|  府守神社
府守神社
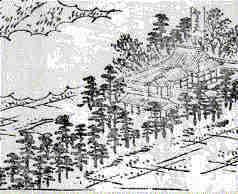
 府守神社
府守神社