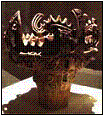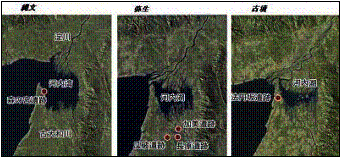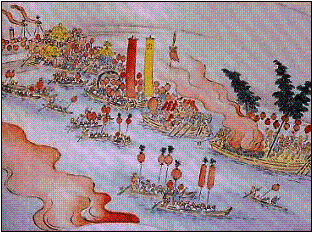|
ウガネット |
火について |
|
|
|
平成十九年七月十六日 神奈備 |
|
| 1.縄文時代の土器 |
|
|
|
|
人面土器 |
調理、灯火、妊婦、容器としての女性 |
|
|
火焔土器 |
火も蛇も萌え立つ、四火柱、四御柱 |
|
|
蛇と女 |
脱皮と出産は永遠の命の連鎖・執念 |
|
|
焼畑農耕 |
『日本書紀』一書第二 |
|
|
軻遇突智と埴山姫から稚産霊が誕生 |
|
|
| 2.火の考古学 |
|
|
焚き火による猛獣からの守り |
|
人面 |
火焔 |
|
|
煮炊き、焼くことで、顎の小型化と脳容量の拡大 |
|
|
土器の作成、食物の保存、焼き畑農耕 |
|
|
スズ(褐鉄鉱)の加工による道具の進歩 |
|
|
淀川・大和川上流の開発進捗に |
|
|
よる河内湖への土砂の流入 |
|
|
火鑽臼と火鑽杵 女と男 |
|
男女を引き裂く時に火が生じる。 |
|
ホトとは火の戸でもある。 |
|
→カグツチの誕生 |
|
|
|
| 3・火の民俗学 |
|
|
火は疫病をもたらす悪霊を追い払う |
|
|
火は人々に暖かい結合をもたらす |
|
|
火はエロスの高揚 |
|
|
火が消えるのは不吉 |
|
|
| 4・火中誕生の貴子 |
|
|
|
|
母神 |
祟りの理由、解けた理由 |
妃神の所業 |
妃神 |
|
| 山幸彦 |
火遠理 |
木花咲耶姫 |
|
|
|
鰐の姿をのぞき見ら |
豊玉姫 |
|
|
火中 |
貞操疑惑 |
|
|
|
れて恥ずかしいと去る。 |
|
|
| 鴨の大神 |
阿遅須枳 |
田霧姫 |
大穴持大神が夢知らせ |
本牟智別に祟る。 |
天御梶姫 |
|
|
唖 |
金属器 |
を聞く |
|
|
執念深い |
|
|
|
| 垂仁皇子 |
本牟智別 |
沙本姫 |
阿麻乃弥加都比女の祟り* |
蛇の姿をのぞき見られ |
肥長比売 |
|
|
唖 |
兄の反乱 |
出雲の大神の祟り** |
て皇子を追いかける。 |
|
|
|
*尾張国風土記 |
**古事記 |
|
| 継体天皇への系図 |
『上宮記』 |
|
|
凡牟都和希王−若野毛二俣王−意富富等王−乎非王−彦主人王−乎富等大公王(継体) |
|
凡牟都和希とは本牟智別(垂仁皇子)か本牟田別(応神)か。鵠神社は誉津別を祭る。 |
|
|
| 5・火と水の祭り 天神祭り |
|
|
|
| 難波長柄豊碕宮の四隅の北西角 |
|
| 疫神や悪神を祓う道響祭→大将軍社 |
|
| 難波堀江とは |
|
| 仏像を流した場所 |
|
| 日本武尊が害する柏の渡りの神を退治 |
| 八十島祭り |
|
| 平城京・長岡京、平安京の排水が流れ下る場所 |
| 穢れを祓う場、菅公も疫神、だからここに天満宮 |
| 水−大海原に押放事(おしはなつこと) |
| 火−火に依る浄化、穢れの祓い、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|