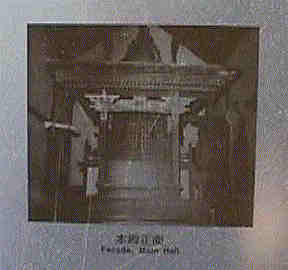伊和志津神社 いわしづ
兵庫県宝塚市伊孑志1−4−3 its-mo
鳥居

交通案内
阪急逆瀬川駅 東に逆瀬川を下る 500m
祭神
須佐之男命、迦具土神
摂社
宝塚水天宮「安徳天皇」
拝殿とその前の石

由緒
伊孑志[イソシ]のお宮と呼ばれる。摂津国武庫郡の式内大社論社である。他に廣田神社の摂社になっている同名の神社が論社である。
このイソシと言う言葉であるが、『日本書紀』仲哀天皇紀に下記のように出てくる。
熊襲の叛乱の知らせを受けた神功皇后は仲哀天皇と穴門の豊浦宮に入り、それから九州へ入った天皇皇后は筑紫の伊覩(伊都)県主の五十迹手(いとて)の服属儀礼をともなった出迎えを受ける。
そこで天皇は五十迹手の「いそいそさ」をほめて「伊蘇志」と言われ、五十迹手の国を伊蘇の国とされ、これが訛って伊覩となったとしている。
伊覩国の場所は現在の福岡県糸島郡(怡土郡と志摩郡を合併)で、邪馬台国のことが記載されている『魏志倭人伝』に「代々王有り」と紹介されている伊都国のことで、古来より大陸・半島への玄関口だった処。
平安時代に作成された畿内の豪族の出自を記した『新撰氏姓録』に「伊蘇志」と言う名前の氏族が載っており、この地を拠点としていたとされる。
それには「伊蘇志臣 滋野宿禰同祖。天道根命之後也。」とある。この天道根命は紀伊国造の紀氏の祖神でもあり、伊蘇志臣と紀直は同祖と言える。
一方、伊都県主の五十迹手は『筑前国風土記逸文』に、「高麗の国の意呂山(おろやま尉山(うるさん))に天から降ってきた日桙の末裔」と名乗ったと記載されている。
また白水社『日本の神々4大和』の中の糸井神社の項に「糸井造は、考合の結果、三宅連あるいは伊蘇志臣と同祖で新羅国天日槍の後裔と見られる。」と出てくる。
これらを勘案すると、『記紀』には出てこない天道根命とは新羅国天日槍命のことであると推論できる。
伊孑志のお宮の祭神は須佐之男命(迦具土神は後に合祀された)となっているが、伊蘇志臣の祖神と考えれば、天道根命もしくは天日槍命と考えることができる。
同時に天日槍命(天道根命)は新羅の王子とされていることからその祖神として須佐之男命が考えられたのかも知れない。 紀氏の秘密系図には、祖神を須佐之男命とされているようだ。
|
由緒 平成祭礼データから
当社は、延喜の御代(約一〇六〇年前)式内の官幣大社として、近郷の尊崇をあつめた古社。御祭神の須佐之男命(すさのおのみこと)は和歌の祖神、学問の守護神、縁結びの神、開発の神。迦具土神(かぐつちのかみ)は火の守り神である愛宕(あたご)の神。又末社、宝塚水天宮は安産の神、水商売の神。
伊孑志、小林、蔵人、鹿塩四村を領家ノ荘(りょうげのしょう)と呼ばれ(摂津志) 当社の小字、良元ノ庄が旧良元村の発生地、古来宝塚の総鎮守であります。(本殿は市指定の文化財・境内は市指定の保存樹林)
以上 |
お姿
逆瀬川沿いの南側に鎮座。中央公民館が隣に出来ているので、この関係で拝殿、覆殿が新築されたものと思われる。
鎮守の森からは小鳥の声が聞こえていた。阪神間もこの辺りまで来ると六甲山系に近く、自然の息吹は少しは残っているようだ。
実に感じのよい神社であった。
拝殿前の説明板の本殿写真
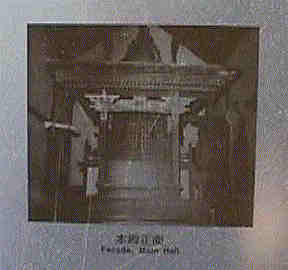
お祭り
4月23日 2日間 春祭
6月30日 1日間 水無月大祓(夏越しの祓、茅の輪くぐり)
7月27日 2日間 夏祭
8月24日 1日間 愛宕祭
10月23日 2日間 秋季大祭(秋祭、文華祭)
兵主神・邪馬台国と天日槍命・赤留比賣命
神奈備にようこそ |