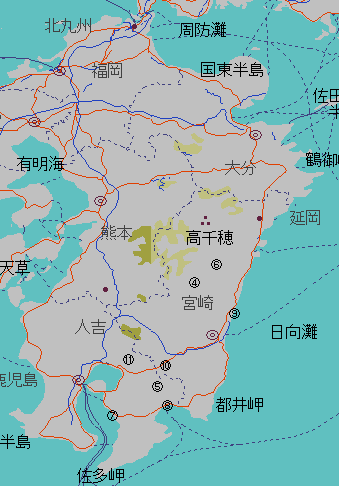韓国宇豆峯神社
鹿児島県霧島市(国分市)上井898 mits-mo 韓国宇豆峯神社
鹿児島県霧島市(国分市)上井898 mits-mo
神社全景と宇豆峯(左)

交通案内
JR国分駅 東南4km
祭神
五十猛命
神体山の韓国岳と大池

由緒
大隅国囎唹郡の式内社。
『続日本紀』によると、和銅七年(714)大隅国設置の翌年に、豊前国から二百戸(約5000人)の民を隼人を教導するために移住させており、その時に彼らが奉斎する韓国神を遷座させて建立したものと伝わっている。
『宇佐記』によると、「欽明天皇三十二年(571)、豊前国宇佐郡菱形池の上の小椋山に祀られたのを当地宇豆峯の山頂に遷座され、さらに国司の進言により永正元年(1504)、現在地に奉遷した。」との記録がある。(以上は社頭説明:国分市教育委員会)
『日本の神々1』によれば、「和銅七年に韓国神だけではなく、鹿児島神宮の一要素となっている八幡神も豊前から遷され、国府のある国分平野の西辺と東辺に配置されたのであろう。」としている。
鳥居と拝殿

『式内社調査報告』には、祭神として天児屋根命も一つの説としてあることを言う。中臣氏の祖神の天児屋根命の孫の天種子命は、神武東征の途中、宇佐にて在地の豪族菟狭津媛を娶った豊前仲津郡中臣郷出身であったとする太田亮の説をあげ、景行紀の熊襲征伐ではこの中臣氏一統の援助が功を奏したと考えるのは、直入中臣神を祀っており、当検校川畔に中臣神が祀られても不思議ではないとする。また中臣氏は播磨国揖保郡で中臣印達神社の例を見るように五十猛神を祀る例がある。
中野播能氏の『八幡信仰史の研究』には、宇佐神宮を祭祀した辛嶋氏は次の系譜を伝えていると記す。
素盞嗚尊-五十猛神-豊津彦-都萬津彦(④妻)-曽於津彦(⑤曽於)-身於津彦(⑥美々津)-照彦(⑦垂水)-志津喜彦(⑧志布志)-兒湯彦(⑨児湯)-諸豆彦(⑩諸県)-奈豆彦(⑪宇豆峯)-辛嶋勝乙女。
④ 宮崎県児湯郡妻町 五十猛命の妹神に抓津姫。都萬神社「木花開耶姫」神名帳考證には抓津姫。
⑤ 鹿児島県曽於郡
⑥ 日向市美々津町 神武天皇の船出の伝承地 立磐神社「住吉三神」
⑦ 鹿児島県垂水市
⑧ 鹿児島県曽於郡志布志町 枇榔神社「乙姫」
⑨ 宮崎県児湯郡 都農神社「大己貴命」
⑩ 宮崎県諸県郡 都城市 早水神社「諸縣君牛諸井」
⑪ 鹿児島県霧島市(国分市)韓國宇豆峯神社「五十猛命」
このような伝承から見ると、当社が鎮座するこの地方を征服したのは、辛嶋氏配下の中臣氏ではないかと、『式内社調査報告』の中で藤井重寿氏は述べている。
辛嶋氏の系譜の地図
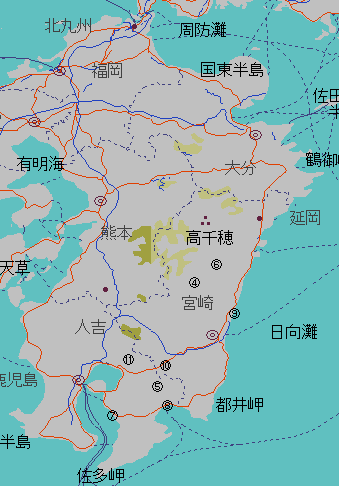
お姿
五十猛神を祀る最南端の式内社。近づくに従ってウキウキ、到着してどきどき、お詣りしてわくわくの感動が順番に襲ってくる。これを感じるために詣でている。
濃い緑の中に鎮座、朱色の社殿にも目が慣れてきた。五十猛神を祀る神社で朱色なのは神奈川にもあった。
本殿
 左が宇豆峯、正面に神社
左が宇豆峯、正面に神社
北向きだから韓国岳や高千穂峯が見えるかも知れないが黄砂が邪魔をした。

お祭り
例祭日 九月 九日 |