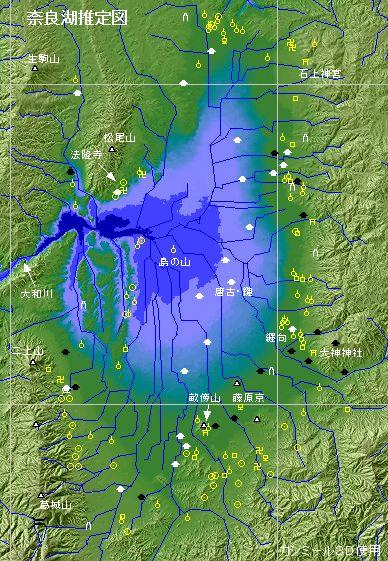吉野河をさかのぼると、尾ある人が井より出てきた。「僕は国つ神、名は井氷鹿」という。吉野首等の祖である。土壌の水銀含有率は 0.0060-0.0078%であり、地下に水銀鉱床が存在することを示している。
3 吉野の山中へ 大蔵神社
山へ入ると、また尾ある人に会った。この人は岩を押し開けて出てきた。名は石押別と言う。吉野国巣の祖である。
岩の中から出てきたのなら磐余であり、磐余彦とは神武天皇の名。熊襲の血は国巣の血と同じ。
4 宇陀の穿邑(うがちのむら) 宇賀神社
宇陀の梟師兄宇迦斯を退治した場所である。兄宇迦斯は押機を造って神武天皇を陥れようとしていたが、大伴連の祖道臣命、久米直等の祖大久米命が兄宇迦斯を本人が造った大殿に追いやり、押しつぶしたのである。兄宇迦斯の血が流れたので血原と言う。これは宇陀が水銀朱の産地として名高く、神武天皇は何を置いてもここを占拠することが東征の大きい目的だった。
地元では慕われていたのであろう兄宇迦斯の魂を祀ったのが宇賀神社である。
歌謡10 ここで久米歌を歌っている。『紀』では神武天皇が歌う。
宇陀(ウダ)の 高城(タカキ)に 鴫罠(シギワナ)張る 我が待つや 鴫(シギ)は障(サヤ)らず いすくはし 鯨(クヂラ)障(サヤ)る 前妻(コナミ)が 肴(ナ)乞(コ)はさば たちそばの 実(ミ)の無けくを こきしひゑね 後妻(ウハナリ)が 肴(ナ)乞はさば いちさかき 実の多けくを こきだひゑね ええ しやこしや
神武天皇側についた弟宇迦斯は宇陀の水取等の祖となった。
5 忍坂の大室で土雲八十建を殲滅。久米歌。 忍坂坐生根神社
歌謡11 八十膳夫を設けて八十建を接待、道臣命の久米歌を合図に刺し殺す。
忍坂(オサカ)の 大室屋(オホムロヤ)に 人多(サハ)に 来(キ)入(イ)り居(ヲ)り 人多(サハ)に 入(イ)り居(ヲ)りとも みつみつし 久米(クメ)の子が 頭(クブ)椎(ツツ)い 石(イシ)椎(ツツ)いもち 撃(ウ)ちてし止まむ みつみつし 久米(クメ)の子等(ラ)が 頭(クブ)椎(ツツ)い 石(イシ)(椎ツツ)いもち 今撃(ウ)たば宜(ヨラ)らし
6 登美毘古を撃とうとして久米歌を歌う。『紀』神武天皇。
歌謡12 みつみつし 久米の子等(ラ)が 粟生(アハフ)には 臭韮(カミラ)一本(ヒトモト) そねが本(モト) そね芽(メ)繋(ツナ)ぎて 撃ちてし止(ヤ)まむ。
また続けて神武天皇
歌謡13 みつみつし 久米の子等(ラ)が 垣下(カキモト)に 植ゑし椒(ハジカミ) 口ひひく 吾(ワレ)は忘れじ 撃ちてし止(ヤ)まむ
更に続いて神武天皇
歌謡14 神風(カムカゼ)の 伊勢の海の 生石(オヒシ)に 這(ハ)ひもとほろふ 細螺(シタダミ)の い這ひもとほり 撃ちてし止(ヤ)まむ
7 兄師木、弟師木を撃とうとして神武天皇が歌う。志貴御県坐神社
歌謡15 楯(タタ)並(ナ)めて 伊那佐(イナサ)の山の 木(コ)の間(マ)よも い行きまもらひ 戦へば 吾はや飢(ヱ)ぬ 島つ鳥(ドリ) 鵜養(ウカヒ)が伴(トモ) 今助(ス)けに来(コ)ね
8 『古事記』では、ここで物部の遠祖邇藝速日命(饒速日命)が登場する。『日本書記』では、大和に先に降っており、当地の神聖王となっていて、長髄彦を殺して神武天皇に帰順するとしている。
久米歌は殆どは神武天皇が歌ったと『日本書記』に記されている。神武天皇は久米族の出身と言うべきだろう。
『古事記』はこれで大和を制圧したとして畝火の白橿原宮に坐して、皇后の選定になる。『日本書記』は、ルートも違うし、戦い殺した原住民が多く記載されているので、以下に紹介しておく。
1 高倉山 
宇陀郡 高角神社
御祭神 高倉下命 由緒 天皇は宇陀の高倉山の頂き登って、国の中を眺めた。
2 丹生川上 
吉野郡 丹生川上神社中社
御祭神 罔象女神 由緒 神武天皇が天神の教示で天神地祇をまつり、厳甓を川に沈めて戦勝を占った聖地という。
顕斎(うつしいわい) 高皇産霊神 ←神武天皇 ← 厳媛
○ 神武天皇が「厳瓮の粮」を嘗されることによって天照大神より一段高い高皇産霊神になる。
○ 厳媛とは高皇産霊神を祭る巫女としての天照大神である。
○ 斎主としての天照大神の地位には厳媛と名づけた道臣命が奉仕。
◎ 神武を天照大神に、厳媛を斎王、に置き換えればそのまま神嘗祭。
◎ 高皇産霊神を天照大神とすれば新嘗祭になる。
神武天皇の丹生川上での顕斎
1.まず、榊を立てて諸神を祭り、 榊:高皇産霊神
2.次ぎに厳瓮の置物があって顯齋が成り立ち、 香山の埴土(倭の物実)で祭祀をする
3.道臣命も斎王としてこれを厳媛と名づけ、 男である道臣命を神格を持つ巫女とし、
4.火 水 米 薪 草 何れも「厳」を冠して、稲魂を炊き、 神聖な上にも神聖な扱い、
5.天皇が厳瓮の粮(おもの)を嘗された。 高皇産霊神が神武天皇に憑りつく。
神武天皇顕彰碑(丹生川上神社)
 鳥見霊畤
鳥見霊畤

3 莵田川の朝原の地 
宇陀郡 丹生神社(雨師)
御祭神 丹生都姫命 由緒 鎮座地の雨師の名は中国の雨の神である。この神社は祈雨、止雨の神徳を持つ。
地元の古老によれば、吉野から分遷したとのことである。
4 女坂の地 
宇陀郡 劔主神社(宮奥)
御祭神 劔主根之命 由緒 磐座である巨磐を割り、運んできて当地で信仰した。宇陀には磐座の欠片を持ってきて祀る習慣があったようで、実に具体的な分祠と言える。
5 男坂の地 
宇陀郡 劔主神社(半坂)
御祭神 建速須佐之男命 由緒
6 墨坂の地 
宇陀郡 墨坂神社
御祭神 墨坂神 由緒 神武紀には兄磯城が炭に火をつけて天皇軍を阻んだとの故事がある。古くは伊勢街道の天神の森に鎮座と言う。現社地から北西1kmの所であり、神武紀の鳥見の霊の畤の跡とされている場所である。
7 磐余の伝承地 
宇陀郡 皇大神社
御祭神 磐裂神 由緒 磐余の伝承地は桜井の河西・安倍付近とする説もある。
8 椎根津彦が占った場所:嬉河原 
宇陀郡 屑神社
御祭神 衝立船戸神、道反之大神 由緒 神社はこの地の氏神だから紹介しているが、神武東征とは関係がない。
椎根津彦と弟宇迦斯が香具山の埴土を取りに行くため敵の中を通り抜ける前に、「我が大君、よく此の国を平定したまうならば無事にこの大任を果たさしたまえ」と祈ったのがこの地と伝わる。
9 金色の霊鵄 
式上郡 宗像神社
御祭神 宗像三女神 由緒 当社の存在は神武東征とは関係がない。
当社から西に鵄谷と言うばしょがある。往時、その谷間から金色の霊鵄が飛び立ったと言い、その谷の隣を勝負谷と言うようだ。