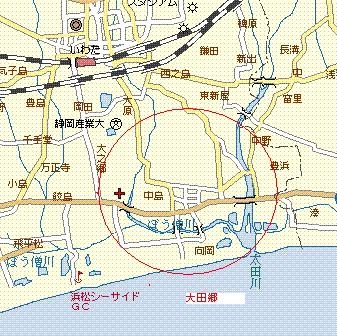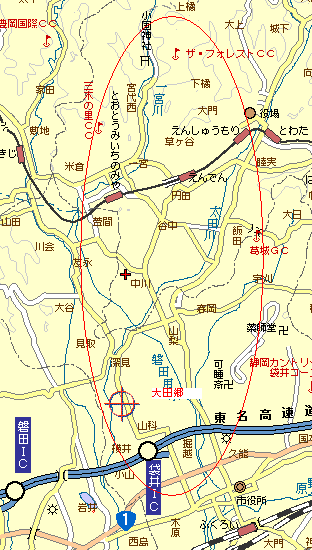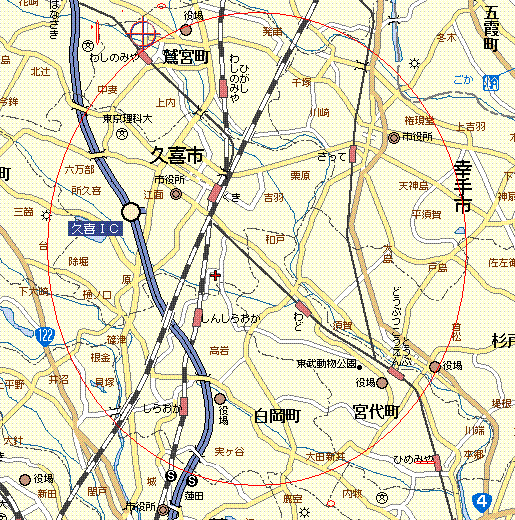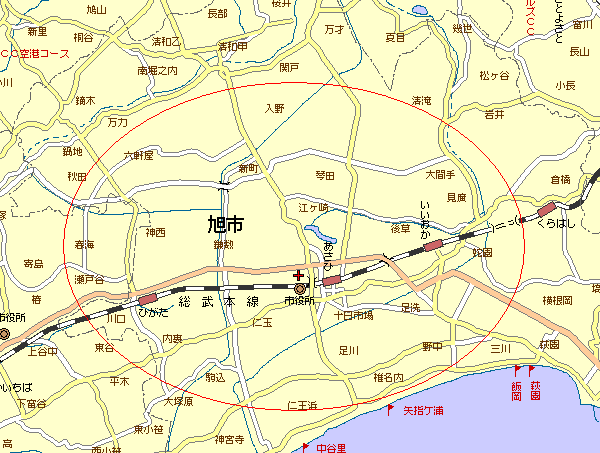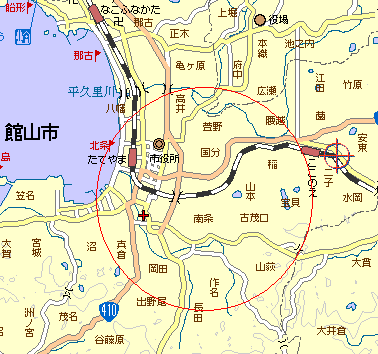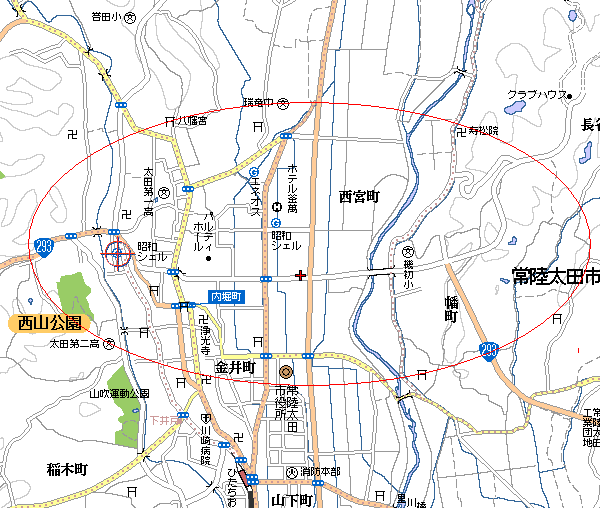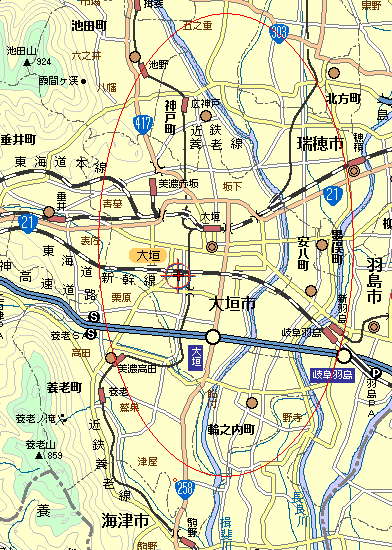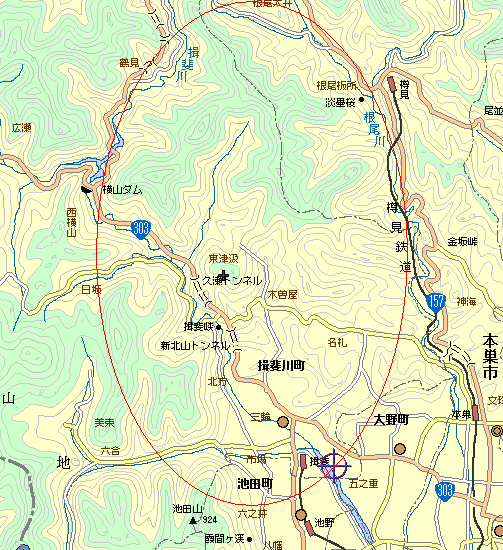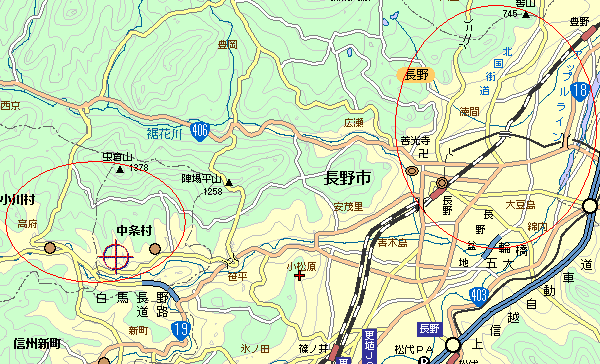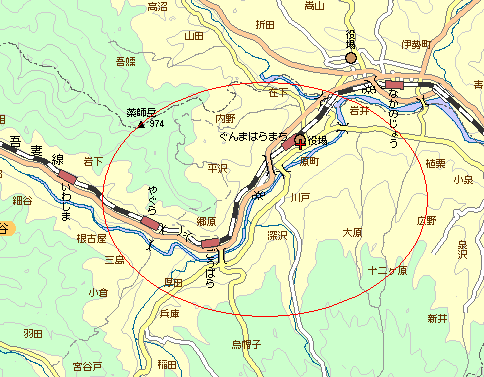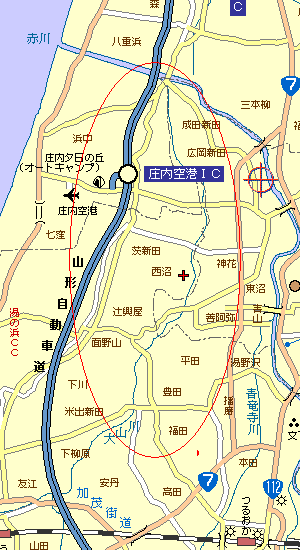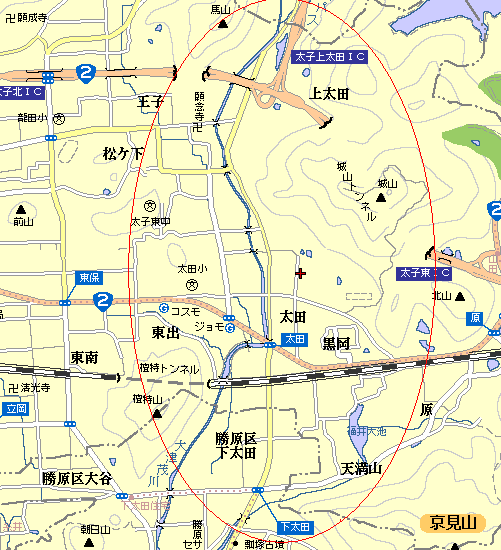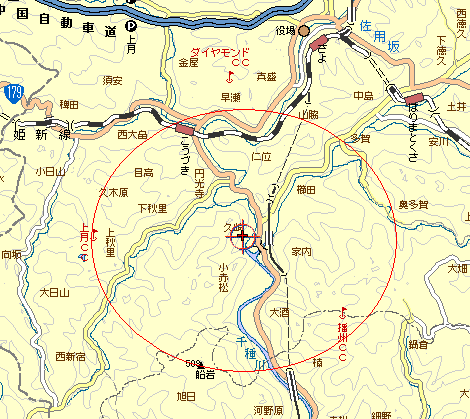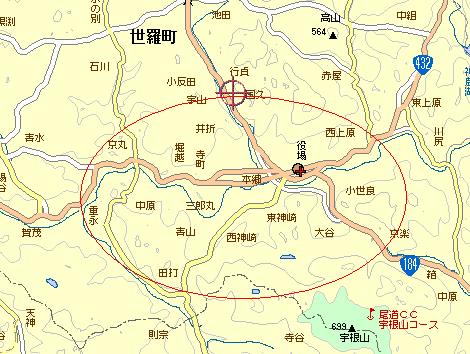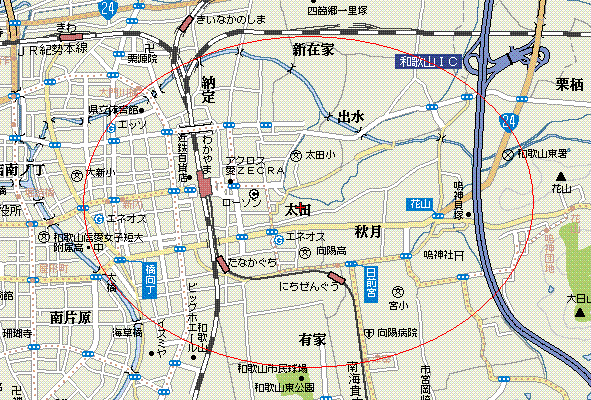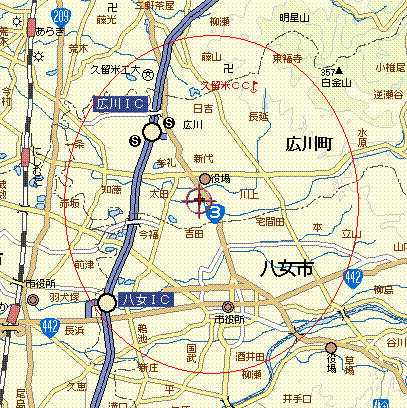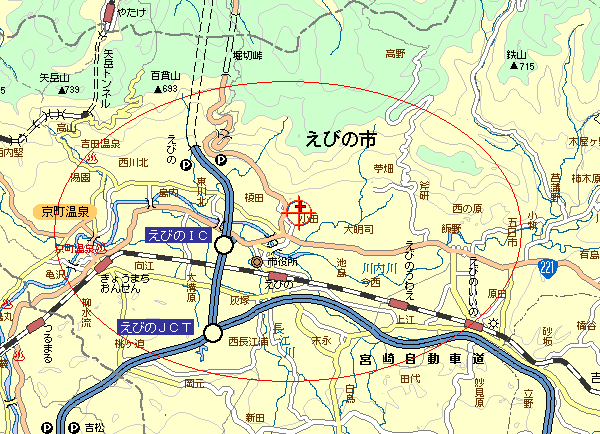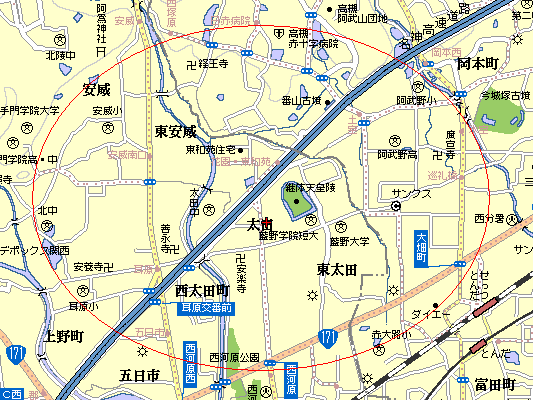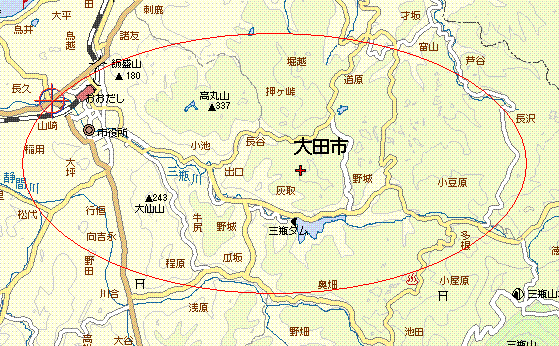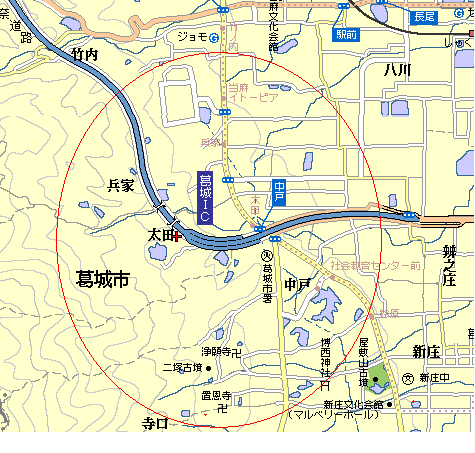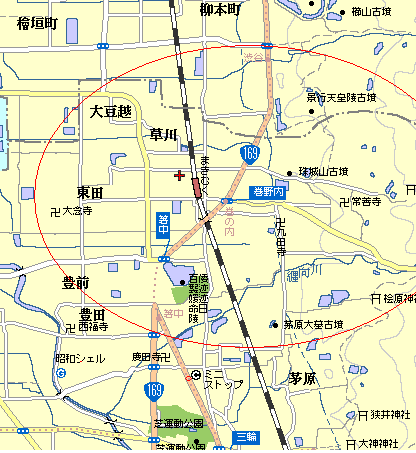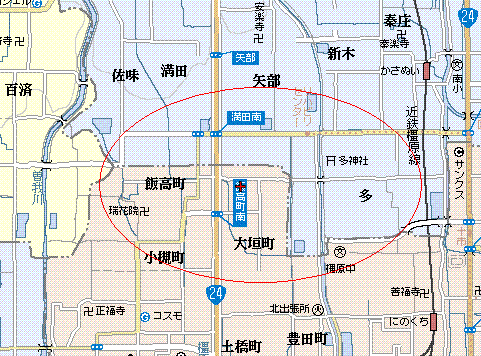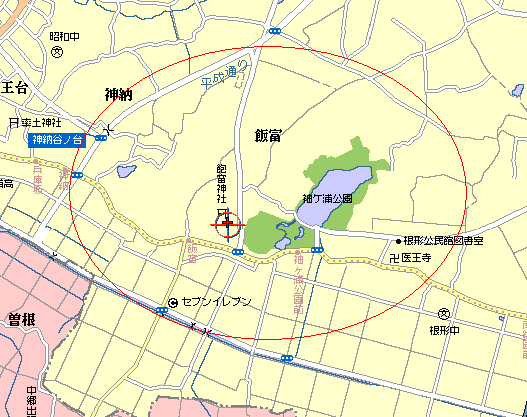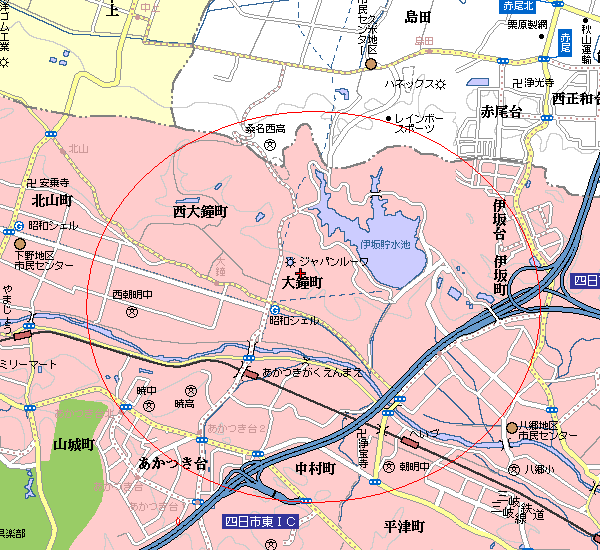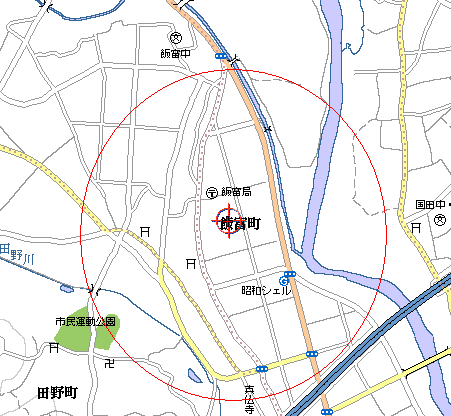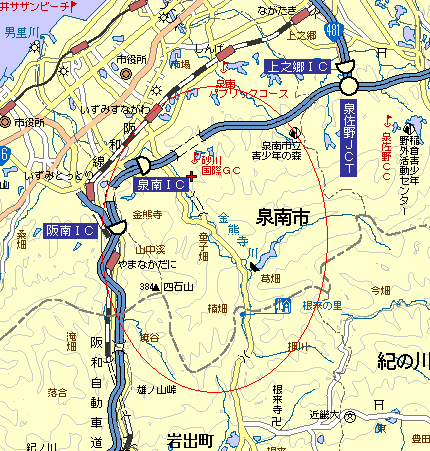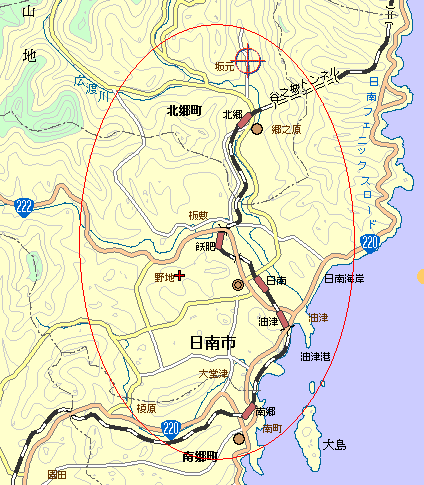|
大垣市、安八町、輪之内町下大榑などに比定されています。
輪之内町に加毛神社が鎮座、祭神は神別雷命となっています。由緒には、鴨君彦坐王の子、神大根王が美濃国の国造となり、その子孫達は西南濃地方に繁行したようで、祖神を祭ったとされています。昭和の『神社明細帳』には祭神は別雷命(猿田彦命)とあるようで、白髭明神と呼ばれていたそうです。
猿田彦命が祭られているとしても、日神の出動に関係がある土地であるとの積極的理由付けは見いだせないようです。
この地域と本巣とは少々離れてはいるものの、加毛神社にいささかかかわる者が本巣国造となったり、また長幡部の祖となっていることと関連があるとも言えましょう。
『常陸国風土記』によれば、綺日女命は天孫降臨に従い、日向の二上峰に降臨し、後に美濃へ移り、崇神天皇の御代に、長幡部遠祖・多弖命が美濃から久慈の当地へ遷したという。常陸国の久慈郡太田郷に、長幡部の神社が鎮座、祭神を綺日女命。多弖命としています。
この神社は織物の神が祭神です。天照大御神も織姫でもあったようで、これは日神と無関係ではありません。日神の登場を準備している神と言えます。
ついでですが、日子坐王が鴨君と称されるのは『姓氏録』で左京皇別下の鴨県主、摂津国皇別の鴨君は日子坐命の後とされており、大国主の後裔ではない鴨君がいたようです。
余談ですが、安八郡安八町西結の結神社(むすぶじんじゃ)は、永享~嘉吉年間(1429~44)頃、小栗判官と別れた照手姫は当社に祈願して判官に再会したという伝承があり、「照手姫の宮」と俗称されているそうです。
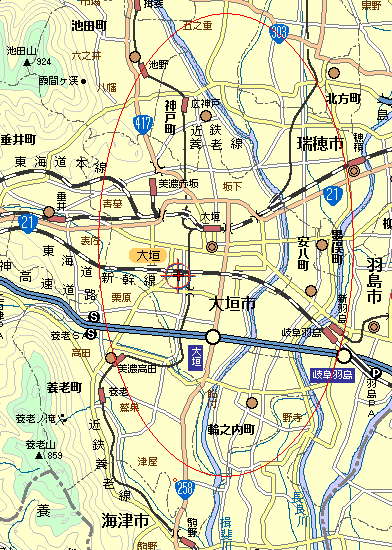
地域の神社
神明神社(天照大神)岐阜県大垣市東前町2丁目9番地
八幡神社(應神天皇)岐阜県大垣市古宮町江東1410番地の1
手力雄神社(天石門別命神)岐阜県大垣市禾森町字本郷2033番地の1
加毛神社(神別雷命)岐阜県安八郡輪之内町下大榑東井堰13017番地
日吉神社(大己貴神)岐阜県安八郡神戸町大字神戸字上ノ宮1番地の1
結神社(天御中主尊 高皇産靈尊 神皇産靈尊 猿田彦神 )岐阜県安八郡安八町西結697番地の2
墨俣神社(墨俣大神)岐阜県安八郡墨俣町大字墨俣264番地 |